王政ローマとは
王政ローマは、紀元前753年~紀元前509年、王によって統治されていた時代のローマをさします。ローマ建国神話によると、ロムルスとレムスという双子がローマを築き、7人の王の統治を経て発展したが、最後は市民の反発が高まり王政は崩壊。ローマは共和政へと移行しました。
ローマと言えば、共和政ローマや帝政ローマが有名ですが、王政ローマの時期は、後のローマの繁栄には欠かせない重要な時期でした。ローマが建国された時、ローマ周辺には既に発展した多くの都市国家があり、かなり出遅れた建国であったことから、周辺国からは小さな未開な集団として軽んじられていました。
しかしローマはそれら周辺諸国を吸収しながら、大きく発展し、やがて、人類史上でも名高い覇権国家へとなっていきます。まさにローマという弱小キャラが、覇権国家という最強キャラになる物語の序章です。今回はそんな王政ローマがいかにして建国され、そして後の覇権国家になるための基盤を築いていったのか紹介したいと思います。
ローマの建国には壮大な伝説があり、その起源はトロイア戦争にまでさかのぼります。トロイアを脱出した英雄アイネイアスの子孫が、やがて都市アルバ・ロンガを築き、その末裔として生まれた双子の兄弟ロムルスとレムスが、数々の困難を乗り越えながらローマを建国しました。しかし、その道のりは決して平坦ではなく、兄弟の対立、政争、そして運命の悲劇が絡み合う物語となっています。
敗北から始まるローマ建国神話
ローマ建国神話は、紀元前1259年から紀元前1179年頃、トロイア戦争(トロイの木馬で有名)で敗れた、トロイアの民を、アイネイアスという青年が、イタリア半島まで導くところから始まります。イタリア半島には当時、ラティウムという地方があり、アイネイアスは、そこの王(ラテン人の祖ラティーヌス)の娘と結婚し、新しく都市ラウィニウムを建てました。都市ラウィニウムは後に、アイネイアスの息子シルビウスが、義母に譲ることになるのですが、息子シルビウスが新たに建てた都市こそが、後にローマの建国者が生まれる都市アルバ・ロンガになります。
当時ラティウム地方には、多くの部族が混在しており、ラテン人はそこで暮らしていた部族の一つでした。ラテン人は、他部族に対抗する為、ラテン系の部族や村を集めたラテン同盟をという連合を組織します。都市アルバ・ロンガはそこの盟主となりました。
 エリッサ
エリッサ
生まれてすぐに捨てられたローマの建国者

出典:Met museum
シルビウスの時代から数えて12代目のアルバ・ロンガ王が亡くなると事件が起きます。王座をかけて、先代の息子、ヌミトル(兄)とアムリウス(弟)が王位をめぐって争い、兄ヌミトルは弟アムリウスによって王座を奪われてしまいます。アムリウスはヌミトルの娘であるレア・シルウィアを巫女にして、子供を産めないようにしました。しかし、彼女は戦争の神マルスによって双子を妊娠し、出産します。その双子こそが後のローマの建国者ロムルスとレムスです。
怒ったアムリウスは、生まれたばかりのロムルスとレムスを、ティベリス川に流して殺そうとしましたが、二人は奇跡的に助かり、狼(ルーパ)によって育てられました。その後、ロムルスとレムスは羊飼いのファウストゥルスに拾われ、成長しました。
軍神マルスは古代ローマ人にとても人気な神様で、古代ローマ人の名前には、マルクスなど、軍神マルスにちなんだ名前が多いです。建国者が、その軍神マルスにつながる人物であるという話は、ローマ市民の愛国心を高め、ローマの強さの一つでもある結束力を強める要因の一つになっていました。
ローマ建国と兄弟の別れ
成長したロムルスとレムスは、自分たちの出自を知ると、アルバ・ロンガに向かい、アムリウスを討ち倒して祖父ヌミトルをアルバ・ロンガの王位に戻しました。その後、彼らは自分たちの都市を建てようとしますが、都市をどこに建てるかを巡って対立します。ロムルスはパラティヌスの丘に都市を築こうとし、レムスはアウェンティヌスの丘を主張しました。
二人は鳥占い(アウグル)で決めようとしましたが、また意見が割れました。レムスが選んだ丘には6羽の鳥、ロムルスが選んだ丘には12羽の鳥が来ました。数ではロムルスの丘が多いですが、先に鳥が来たのはレムスの丘だったのです。「数が多い」ことを重視するロムルスと、「先に来た」ことを重視するレムスで意見が割れたのです。ロムルスはパラティヌスの丘に城壁を築き始めましたが、レムスはそれを馬鹿にして飛び越えました。それに激怒したロムルスは、弟であるレムスを殺し、「国境を脅かす者は、誰であれこのような運命を迎えるであろう」と宣言しました。紀元前753年4月21日、ロムルスはついに都市を完成させ、その都市を、自分の名前にちなんで「ローマ」と名づけました。
レムス殺害の話には別の説があり、レムスを殺したのはロムルスとは別の人物で、ロムルスは国境を愚弄した弟の殺害を認めながらも、立派にレムスを埋葬したという話もあります。
王の補佐組織 元老院の設立
ロムルスはローマ建国後、統治には助言者が必要であると考え、ローマの主要な家族の中から年長者を選び、元老院(Senatus)を構成しました。Senatusはラテン語で年長者を意味するSenexに由来し、元老院は賢明な長老たちの集まりとして機能しました。元老院といえば強い決定権を持って、ローマの統治や、政治を行っていた集団のイメージがありますが、それは共和政ローマ時代の元老院で、王政の頃の元老院は、あくまで王の補佐集団であり、政策や戦争、外交に関して王に助言をしたり、王が死亡した際に、新たな王を選ぶための選挙を監督するのが主な役割でした。ロムルス以降の王たちも、元老院を拡大・強化し、王政ローマ後期には、元老院の議席は200名ほどまで増えていました。
市民が男しかいない!よし女を拉致ろう作戦

出典:Met museum
ロムルスは、ローマの人口を増やすため、人々を呼び込もうとしましたが、ローマはまだ小さな未開な都市と見下されており、誰もローマに移住してくれませんでした。ロムルスは他国の逃亡者や亡命者を接客的に受け入れ、ローマの人口は順調に増加していきましたが、一つ問題がありました。それは、ローマに男しかいないということです。女性も呼び込もうとしましたが、誰も来てくれませんでした。そこでロムルスはとある作戦を実行します。それは他の都市から女を拉致って来よう作戦です。
ローマの北東の位置には、サビニ人と呼ばれる屈強な人々が住んでいたのですが、ロムルス達は、そのサビニ人を祭りに誘い、そこに来たサビニの女性達を拉致しました。当然サビニ人達は怒り、拉致られたサビニの女性を取り返そうと、ローマに攻めてきましたが、ここで奇跡が起こりました。拉致られたサビニの女性が、ロムルス達をかばい、ローマとサビニを仲介しました。結果、ローマ人とサビニ人は合併することになるのです。最初はロムルスとサビニの王ティトゥス・タティウが共同統治することになったのですが、サビニ王が早くに他界してしまい、結果ロムルスがすぐに単独王に返り咲くことになります。
ローマが世界の覇者になった要因はいくつもありますが、その一つが「敵をもローマに同化させる力」です。その力の片鱗が、既にこの頃から発動していたのです。
サビニ人たちはとても強く、一説ではスパルタ教育で有名なギリシャの都市「スパルタ王国」からイタリア半島に移住してきた人達だと言われています。ローマは女性だけでなく、屈強な戦士も手に入れることになりました。
初代王英雄ロムルスの死
ロムルスの死因には、いくつかの異なる説が伝わっています。彼はローマ建国の英雄であり、その死も神秘的なものとして語られることが多いです。今回は有名な4つの説を紹介します。
① 天に召され、神になった(アポテオーシス説)
最も有名な説で、ロムルスは神々によって天に引き上げられたとされる。ある日、ロムルスが軍隊を点検していると、突然激しい嵐と暗雲に包まれ、雷鳴が轟き、彼の姿が消えた。兵士たちは混乱し、ロムルスの行方を探したが、見つからなかった。その後、彼の親しい友人であったプロクルス・ユリウスが、「ロムルスが神クィリヌス(Quirinus)として天に昇り、ローマを守る存在になった」と証言。ロムルスはクィリヌス神として祀られ、後にローマの国家神の一柱となった。
② 元老院による暗殺
彼は独裁的な統治を行い、元老院の意見を無視することが増えていた。そのため、元老院議員たちが彼を暗殺し、証拠を隠すために遺体を細かく切り刻み、それぞれが服の中に隠して持ち帰った。
③ 嵐で死亡
彼が公の場で演説していたとき、突然嵐が起こり、落雷によって死亡した。しかしローマ人は偉大な王の死を単なる事故とはせず、神に召されたと考えることで、彼の神聖性を強調した。
④ 戦闘中に行方不明
ロムルスは生涯、ローマの拡張と防衛に尽力し、多くの戦争を指揮していたので、彼の死も戦場での戦闘中に行方不明になったのではないかという説もある。戦死したが、死体が見つからなかったため、後の伝説で神になったという話に変わったとされた。
ロムルスはローマの象徴的な創始者であるため、「神になった」という神話が公式に採用されました。しかし、暗殺説や事故説も合理的な解釈として考えられています。
 エリッサ
エリッサ第2代王ヌマ・ポンピリウス – 嫌々だったが偉大な王に。
英雄ロムルス王亡き後、誰がローマの次の王になるか、ラテン人の中から王を出したい勢力と、サビニ人の中から王を出したい勢力で争っていました。最終的に王に抜擢されたのは、サビニ人のヌマ・ポンピリウス。ヌマは非常に敬虔で哲学的な人物であり、王になる前は、哲学や農業をしながら静かに暮らしていました。ヌマはとても無欲な人物で、王になることを拒否していましたが、ラテン人派の人々も、ヌマなら良いと認めたことで、ヌマは王になりました。
しぶしぶ王になったヌマでしたが、後世にも語り継がれる偉大な王になります。ヌマは戦争によってではなく、法と信仰によってローマを強くしようと考えました。ヌマは宗教制度を確立することで、神々への信仰を社会に根付かせました。これは後にローマ人の愛国心を高める結果となります。ほかにも、ローマの暦を、12か月で1年と定めたり、宗教儀式の祝日を定めることで、ローマ人の生活に規律をもたらしました。また、貧しい人々のために、土地の再分配を行い、農業を促進させます。
紀元前673年にヌマは約80歳で他界しましたが、彼の死後、ローマ人は彼を偉大な法と宗教の王として崇めました。
ヌマの統治では軍事的な拡大がなかったため、一部からは不満もありましたが、彼の宗教制度は後のローマの発展に大きく寄与しました。
第3代王トゥッルス・ホスティリウス – ロムルスの出生地アルバ・ロンガを破壊
ヌマの次に王となったトゥッルス・ホスティリウスはとても好戦的な人物で、戦争によるローマの勢力拡大を進めていました。そんな時、ローマとアルバ・ロンガの国境沿いで争いが生じ、これを口実に、ホスティリウスはアルバ・ロンガに宣戦布告します。戦争が始まると、ローマとアルバ・ロンガの軍隊が対峙しましたが、両軍とも決定的な戦いを避け、最終的に決闘で決着をつけることになりました。
結果、ローマ側の戦士が勝利し、アルバ・ロンガはローマに従属することになりますが、アルバ・ロンガ王メトゥス・フフィウスは、ローマのライバル都市フィデナがローマと戦争を起こすと、ローマを裏切りました。しかし、この戦いもローマが勝利し、フェディナとアルバ・ロンガの多くの住民はローマに強制移住。フェディナはローマ人が占領し、アルバ・ロンガは完全に破壊。メトゥスは馬で体を引きちぎられて処刑されました。ここに、ローマ建国者ロムルスの出生地であるアルバ・ロンガは滅亡しました。
この戦争の勝利によって、ローマの領土と人口は大きく増加し、ラティウム地方における、ローマの軍事的・経済的な支配権が強化されました。ホスティリウスは、ローマを軍事大国へと導いた王として歴史に名を残しましたが、後に神々を軽んじたことが原因で雷に打たれて死亡したと伝えられています。
強制移住となったフェディナとアルバ・ロンガの住民は、奴隷にされることはなく、市民権を与えられました。また、王メトゥス・フフィウスは処刑となりましたが、貴族階級はそのまま、貴族の地位を維持されました。後に、ローマで絶大な権力を握るユリウス・シーザーの祖先は、この時にアルバ・ロンガから移住してきた貴族です。これは敗者が奴隷なるのが当然の古代では珍しいことで、この寛大さこそがローマの強さである「敵をもローマに同化させる力」の所以なのかもしれません。
 エリッサ
エリッサ第4代王アンクス・マルキウス – インフラ整備と領土拡大
アンクス・マルキウスはヌマ・ポンピリウスの孫であり、その影響を強く受けていました。ヌマが宗教と法律を重視した王であったのに対し、アンクスもまた、ローマの精神的な安定を重視した政策を推し進めました。しかし、彼は単なる宗教的な統治者ではなく、先代の王ホトゥッルス・ホスティリウスの軍事的な方針も理解していました。そのため、彼の治世は、平和的な発展と軍事力の拡大というバランスの取れた政策が特徴的です。
彼の最も重要な功績の一つが、ローマ初の港オスティアの建設です。オスティアはティベリス川の河口に位置し、ローマの商業の発展において重要な役割を果たしました。これによって、ローマは塩やその他の物資を効率的に輸送できるようになり、経済が大きく発展します。ほかにもローマの城壁を拡張したりと、次々とインフラの整備を進め、彼の時代に建設された橋や道路は、ローマが後に強大な国家へと成長するための基盤となりました。
アンクス・マルキウスは平和的な政策を重視していたものの、必要な場合には軍事力を行使しました。彼の治世の間に、ローマはラティウム地方の都市を次々と征服し、領土を拡大していきました。征服した土地にはローマ市民を入植させ、ローマの文化や法律を広める政策を取りました。このような方法は、後の共和政ローマや帝政ローマでも続けられることになります。
アンクス・マルキウスは紀元前617年頃に死亡したと伝えられているが、その死因についての明確な記録は残っていないません。しかしアンクス・マルキウスは自然死・病死した可能性が高いとされています。彼はローマの拡張とインフラ整備に尽力した王であり、戦争にも勝利していたため、暗殺される理由があったとは考えにくいからです。
第5代王タルクィニウス・プリスクス – エトルリア人の血を引く王
ローマは今まで、ラテン人またはサビニ人が王になっていたいましたが、彼は初めてエトルリア人の血を引く者として王になりました。前王アンクス・マルキウスの死後、彼はその子供たちを出し抜き、自ら王位に就いたと言われています。
彼はローマの街をさらに発展させるため、エトルリア人の建築技術を導入し、大規模な建築事業を進めました。代表的なものとして、サーカス・マキシムスの建設が挙げられます。これはローマで最も古い競技場であり、戦車競争などの大規模な催しが行われる場所となりました。また、ローマの排水システムを向上させるため、クルアカ・マキシマという巨大な下水道を建設し、都市の衛生環境を整備します。この下水道は、後の帝政ローマ時代にも引き継がれ、都市計画の基盤となります。
軍事面では、ローマとは別の都市に住むラテン人やサビニ人との戦争を行い、ローマの領土を拡大しました。特に、エトルリア人の軍事技術をローマに持ち込んだことは重要で、ローマ軍の戦術や装備の向上に貢献したとされています。また、彼は元老院の議員を100名増員し、政治体制の強化も行いました。
ローマといえば優れた建築技術ですが、実はローマの建築技術はもともとエトルリア人のものでした。ローマの強さの一つに、敵の技術も吸収していく力がありますが、エトルリア人の建築技術や軍事技術の吸収はまさにその良い例です。
 エリッサ
エリッサ第6代王サーヴィウス・トゥッリウス – 低い身分から王に。社会制度の改革に貢献
彼の出自についてはさまざまな伝説が残っていますが、最も有名なのは彼が奴隷の出身であったという説です。彼は先代の王タルクィニウスの宮廷で育てられ、王の信頼を得ていました。タルクィニウスが暗殺された際、王妃タンキルが彼を次の王に推し、彼は混乱の中で権力を掌握しました。
彼の統治の中で最も重要なのは、ローマ社会の階級制度を再編成したことです。彼は市民を財産に基づいて分類し、軍事や政治への参加を整理しました。これにより、財産を持つ市民がより大きな役割を果たせるようになり、ローマの統治体制がより安定しました。具体的には、彼はケントゥリア制度の確立と定着をし、市民を軍務に応じた部隊に分類しました。この制度は、後の共和政ローマにおいても重要な役割を果たしました。
彼はローマを防衛するために、セルウィウス城壁を築きます。この城壁は、後の時代に何度も修復されながらも長く使用され、ローマの防衛力を向上させました。さらに、彼はローマの神々を重視し、エトルリア風の神殿も建設もしました。特に、フォルトゥナ(運命の女神)の崇拝を奨励したことで知られています。
彼の統治は、多くの改革を成功させましたが、義理の息子タルクィニウス・スペルブスがクーデターを起こし、最終的に殺害されました。一説では、階段の上から転落させられたとされ、逃げようとしたところ、タルクィニウスの配下によって残忍に殺害されたと伝えられています。しかも実の娘であるトゥッリアは夫のクーデーターを共謀しており、まだ少し息があった父を馬車でひき殺したとも言われています。この事件が起こった場所は、後にトゥッリア街道と呼ばれ、呪われた通りとして知られるようになりました。
第7代王タルクィニウス・スペルブス – 英雄ロムルスから7代続いた王政の終焉
タルクィニウス・スペルブスの統治は、ローマ王政最後の時代を象徴するものであり、彼の支配は暴政によって特徴づけられていました。彼は正当な継承ではなく、前王であったサーヴィウス・トゥッリウスを暗殺することで王位を奪いました。彼は即位後、元老院を軽視し、貴族層を遠ざけることで独裁的な統治を進め、その結果、彼の政治は恐怖と弾圧によって支えられるものとなります。
彼はカピトリヌスの丘に壮大なユピテル(ローマの守護神)の神殿を建設し、ローマの威信を高めようとしました。しかし、これらの工事には多くの市民が強制的に動員され、大きな負担を強いられることになりました。そのため、彼の支配に対する市民の不満は次第に高まっていきます。軍事的にはラティウム地方の支配を強化し、ローマの領土を広げようとしましたが、戦争の成果を市民に還元することはなく、さらなる反発を招く結果となります。
タルクィニウス・スペルブスの暴政、そしてローマの王政に終止符を打つきっかけとなったのは、彼の息子であるセクストゥス・タルクィニウスによるルクレティアへの強姦事件でした。ルクレティアはローマの名門貴族の女性で、しかもセクストゥスとは親戚関係でした。セクストゥスは、夜るにルクレティアの寝室に忍び込み、彼女を強姦しました。その貞操と名誉を傷つけられた彼女は、夫と家族にその事実を告白した後、自ら命を絶ってしまいます。この悲劇はローマ市民の怒りを爆発させ、ルキウス・ユニウス・ブルトゥスを中心とする反タルクィニウス派が立ち上がるきっかけとなりました。彼らは市民を結束させ、ついにタルクィニウス・スペルブスとその一族はローマから追放されます。
タルクィニウス・スペルブスは追放された後も、ほかの都市と手を組んで、ローマを奪い返そうとしますが、共和政に移行したローマによって阻まれ、ローマの王位を奪還することは叶いませんでした。
 エリッサ
エリッサ共和政ローマ – 元老院と市民によるローマの幕開け
紀元前509年、ローマ王政は終焉を迎え、共和政が誕生しました。ローマの市民と元老院は協力しながら、絶対的な権力を持たせない、市民と元老院のローマをモットーに、新たな政治体制を整えました。ローマがローマたる所以の共和政はどのような体制だったのか、いくつか紹介したいと思います。
王に代わる二人の執政官を設置
共和政ローマは、王のような絶対的な権力を一人に持たせないため、任期1年の執政官(コンスル)を2名選出し、彼らが王の代わりにローマを統治しました。この仕組みにより、一人が独裁者になるのを防ぎ、互いに牽制しながら国家を運営する体制が整えられました。
現代使用されているコンサルタントという言葉は、ローマの執政官(コンスル)が語源となっています。
庶民を守る護民官の設置
共和政の初期、庶民たちは政治的権利を求め、庶民と元老院の間に深刻な対立が生まれました。そこで元老院は、護民官(トリブヌス・プレブス)という新たな役職を作ることにします。護民官は元老院や執政官の決定に対して拒否権(ウィトー)を行使できる力を持ち、庶民の利益を守るための重要な役割を果たしました。
現代でもEUにはオンブズマンと呼ばれる、市民の権利を守るために政府の決定や行政機関の行動を監視し、不正や不公平があれば介入する役割を持っている機関があります。これはローマの護民官を再現したものです。
十二表法の設立
これはローマで初めて成文化された法律であり、貴族が彼らに都合よく法律を運用するのを防ぎ、すべての市民に法の内容を明確に示すものでした。この法律の整備によって、庶民の権利が一定程度守られるようになり、共和政の基盤がより強固なものとなりました。
 エリッサ
エリッサ
まとめ
王政ローマは、共和政ローマや帝政ローマに比べて、あまり注目されませんが、ローマが覇権国家になるために必要だった基盤が、確実にこの時期に築かれました。建国当初、弱小で見向きもされていなかったローマが、多くの困難を経験しながら、成長し、やがて覇権国家になる物語の序章ともいえる王政ローマ時代は、神話が混じっていることもあり、どこか神秘的な印象があります。
 エリッサ
エリッサ




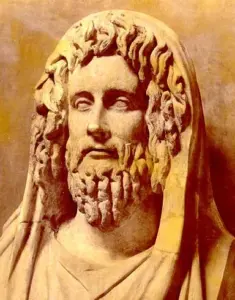
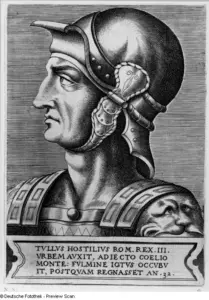
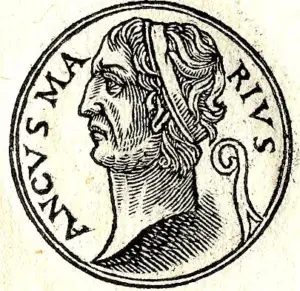









コメント
コメント一覧 (1件)
ローマの建国史を見てると、出遅れたとか関係ないって思えるね。